|
赤須喜久雄・諸国行脚「奥の細道の巻」・・・・・・< その1―③ >
③ 奥の細道 PART 2 <1982年(S57)4月21~24>
「 やわらかに 柳青めるきたかみの
岸べ目に見ゆ 泣けと如くに 」 <啄木>
≪日本一のコンサートホールと医療行政視察≫ ・共産党駒ヶ根市会議員団
| ・4月21日(水) |
PM9.00 自動車にて駒ヶ根市出発 |
| ・4月22日(木) |
AM8.30 宮城県小牛田町・芝居ホール視察
AM9,30 岩出山町・北海道開拓
AM10,30 中新田町・バッハホール。党議員と懇談
PM3,00 岩手県平泉町・中尊寺
PM4,30 岩手県江釣子町・ジャスコ視察(大型店問題)
PM6~7,00湯田町・共産党議員と懇談(国保受診率岩手1位)
<宿泊=湯田町湯本温泉> (駒ヶ根~湯田=820㎞) |
| ・4月23日(金) |
AM9,00 岩手県沢内村視察・保険事業“世界一”
AM11,00 民芸博物館(マタギのすべて)
PM2,00 宮城県迫町・共産党議員と懇談
PM3,30 涌谷町(みちのくの産金事始め・奈良時代)
PM5,00松島・奥松島<宿泊=七ヶ浜町>
(沢内―松島=220㎞) |
| ・4月24日(土) |
AM8,30 塩釜・中卸市場
AM9,30 多賀城址視察(奥州小幕府、奈良~平安時代)
AM10,00 東北歴史資料館
AM11,00 青葉城
AM12,00 仙台・宮城ICより東北自動車道にのる
PM10 駒ヶ根着の予定が、25日になっていた。
(松島―駒ヶ根=625㎞) 走行距離総計=1665㎞。 |
かつて、奥の細道行脚をしたのは、8年前―1974年だった。
その時も、今回も共産党議員団の研修旅行である。前回は電車で行ったが、今回は自動車で、“うたなどつくる”という余裕もなく、まったく忙しい旅であった。
この旅の記も、帰ってからペンをとったものである。だが、芭蕉も立ち寄った多賀城址や中尊寺に、今回は寄ることができ本当に良かった。
また、青葉城にも行き、高いところから杜の都の春の姿・・・ 欅の芽吹きをとくと見てこれたことは、人生にとって新たなプラス面となった。
芭蕉をはじめ、宮沢賢治、石川啄木、柳田国男の遠野物語、さらには岩手県湯田町では正岡子規にも接した心豊かな旅であった。
奈良時代の遺跡から平安時代、戦国、江戸と・・・ さらに今日から未来に向けてのバッハホールと芝居ホール、また沢内村の医療と生産活動など大いに学ぶことばかりであった。
4月21日
今日は忙しかった。
AM9時30分、三重県津市などの共産党議員団4人が下水道の件で駒ヶ根市の共産党議員団の話を聞きにきた。
AM11時、中途退席し、赤穂公民館で教育長、次長と東伊那小学校の校舎改築にともなう庭園整備の件で話し合い。
PM1,30― 伊南農協総代会。3件の動議を出す。うち2件採択された。特筆すべきことは、手数料を引き下げる動議が通ったことである。PM6,30までかかった。
PM9,15分出発。雨が一段と激しく降る。2,3日前から引いていたカゼも悪化する一方であった。(以後、5月1日のメーデーに声が出ず、挨拶を変わってもらう。5月6日の、建設委員会の旅行で°道後温泉に泊まるまでつづいた。なぜかここで治る)
4月22日
雨は福島あたりまで降り続いたが、夜明けとともにやんだ。
福島の手前の二本松市あたりでは、眠気覚ましに“ 千恵子抄 ”を歌いながら北上。・・・・・ 東京の空、灰色の空、本当の空を ・・・
仙台の北50Kmの古川ICで東北自動車道をおりる。芭蕉は、「奥の細道」のなかで、この古川市内にある小さな橋 “緒絶えの橋” のことを「歌枕」の地であるとふれている。
AM8,30-9,00 小牛田町の芝居ホールを見学。
8年前、この町の国鉄の駅で「 Have you visitet to see in MATUSIMA? 」 とイタリア人に聞いたところである。
地方文化の拠点として、また「公園の中の街づくり」のテーマに感銘する。
AM9,30-岩出山町の北海道開拓への貢献について視察。芭蕉は、平泉から鳴子の湯に向かったが、その時ここで一泊している。
AM10,30―中新田町の文化会館” バッハホール “ へ。
「いま、なぜバッハなのか? ・・・ このホールを訪れる少年達が何かを感じ取ってくれれば。その成果を数十年後に期待する。」 ・・・ という、町長の次の世代にかける主張に我同意する。
この町の共産党議員と昼食をともにして語り合う。彼は(町議)、「やませが吹いて凶作だというのに、バッハもなにもあるものか。(町長)自分が国会議員になるための布石に利用している。」と言っていた。
≪中尊寺≫ 東北自動車道を一路北上。中尊寺下に到着。徒歩にて金堂に向かう。
前々から、一度は訪ねてみたいと思っていたところであり、どんな山奥か・・・と思いきや、平野の中の小高い山(丘)という感じで、少し気落ちはしたが、藤原三代の栄華の跡を一目見るために、足は力強く上へ上へと急いでいる。
・・・ 三代の栄耀一瞬のうちにして ・・・ を想起しながら右に中尊寺の本堂、さらに登って光堂にいたる。
藤原四代のミイラの映画を見て、いよいよ金色堂である。
“ 夏草や つわものどもが 夢の跡 ”
“ 五月雨さみだれの 降り残してや 光堂 ”
この中尊寺境内から北上川も、それへ注ぎ込む衣川もよく見える。
“ やはらかに 柳青める北上の 岸辺目に見ゆ 泣けどごとくに ” と啄木は詠ったが、中尊寺見た北上川は、川幅いっぱいに水をたたえ、とうとうと流れており、天竜川とは違ったおもむきであった。夜、北上川のほとりで、ギター片手に"北上夜曲”をうたったなら ・・・・・
この地は、かの勇将!源の義経の最期の地でもある。
三日ほど前から風邪気味だったが、昨夜の強行軍でさらに悪化してしまった。風邪をビールで治そうと昼食の時に2本飲み、この中尊寺まで寝てきたが、これから酔いがまわる…というときに着いてしまい、意気とは逆に全く参ってしまった。

金色堂前 |
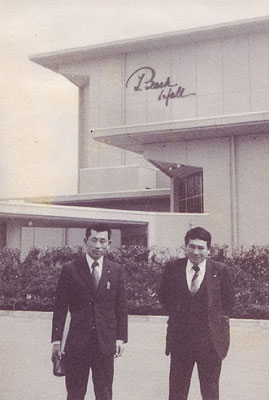
バッハホール前 |
さらに東北道を北上する。そして、昔の黒沢尻・いまの北上市にある北上・江釣子ICにつく。
3月18日、東京地裁の大型店判決で話題となった、「江釣子えずりこ村のジャスコ」を見学し買い物をする。このジャスコは、インターを出たところにあり、モータリゼーションの新時代のもとで、インター前に大型店とは・・・ 私の脳裏に閃いたのは、かねてから考ええていたことではあったが、駒ヶ根IC前の空き地利用について、第三セクターで市と農協と商工会議所などによって、駒ヶ根の「 特産物直売卸売センター」を設けて、中央道の通過交通の人でも「なにか」を買ってゆけるようなものを・・・ まさにいいアイデアだ・・・ と友2人に構想を披露した。
≪岩手県・和賀郡≫
江釣子から、一路夕陽に向かって西へとはいる。奥羽山脈の山並みは、遠くから見たときには、山の頂にのみ雪がかぶさっていたが、湯田町が近づくにつれて低い山の北側などにもたくさん残雪があり、また道路わきの土手の“ふきのとう”も、5~10㎝に伸びているが、つい先頃春を迎えたような・・・ 早春の香りいっぱいである。
“錦秋湖”のほとりの大分改良が進んだ国道を西へ進む。
道端の杉の木の根元も、雪や吹雪のために折れ曲がっており、なるほど雪の多い地方だと痛感する。
今夜は、沢内村の手前の湯田町の「湯本温泉」に泊まることになっている。
湯田町議の坂本さんの息子の嫁さんの実家が旅館をやっているということで、その「和賀旅館」を手配してくれていた。
湯田町は国民健康保険での受診率が岩手県第一位である。坂本さんとそれらの話をしながら懇談した。
坂本さんから「今夜はとことん飲もう」と誘われたが、昨夜9時過ぎに駒ケ根を出て湯本温泉に着いたのは夕方の6時頃で、820㎞の長旅の疲れで残念ながら床に就く。
≪4月23日(金)天気・快晴≫
明治の文豪・正岡子規は、この温泉に明治26年、27歳の時に秋田県から入り泊まっている。そして、翌日「黒沢尻」に出ている。
 “ ひぐらしや 夕日の里は 見えながら ” (子規) “ ひぐらしや 夕日の里は 見えながら ” (子規)
“ 白露に 家4,5軒の 小村かな ” (子規)
“ 山の湯や 裸の上の 天の川 ” (子規)
“ 秋風や 人あらわなる 山の宿 ” (子規)
その30年後、宮沢賢治が訪れている。
“ げに和賀川の赤さびの
けわしき谷の底にして
春の真昼の雪しろの
浅黄の波をながしたり “ (春のスケッチ)
大正10年ごろは、10をこえる銅鉱山が和賀川筋にひしめいていたという。その頃の風景であろう。
≪沢内村・生命行政の成果=日本一≫
今日は待ち望んだ沢内村の視察である。坂本さんが同行してくれた。
長野県では、4月末となると平地には雪が全くないのに、道端の土手の北側にはまだ雪が残っている。
そして、いたるところに“蕗のとう”の花が咲いている。早春である・・・。
家の造りも雪国風であり、軒下に積んである薪も1mくらいの長さがある。いろりで焚いているのだろうか・・・?
新聞、テレビ、雑誌、さらにラジオドラマにもなって、全国に紹介された、この医療の村・沢内村は、昭和30年代、山村の宿命と言われた「豪雪、病気、貧乏」に打ち勝つ村づくりをしようと取り組みをはじめ、健康づくりでは「赤子がコロコロと死んでたまるか」と、ゼロ歳児からの医療無料化や老人医療は60歳から無料(S36)を実施。人口5000人足らずの村に、保健婦4人を配置(世界一の高率)して、村民全員の健康管理台帳を活用するなど素晴らしい健康づくりをなしとげてきた。
当時、国はそのような施策に対して「やりすぎだ」として、「交付税の打ち切り」「法令違反」などという脅しをかけてきたが、当時の深沢村長を先頭に「健康を守ることは、憲法の理念だ」・・・ と、敢然とたたかってきたことや「必要なことは、どんな障害があってもやりぬく」という基本姿勢に貫かれた姿に深い感銘を受けた。
このような実践の結果として、全国に先駆けて60歳以上の老人医療費無料制度を実施して、予防を中心とした保健事業の推進で逆に医療費を下げてきたのである。
沢内村のお年寄りの医者にかかる率(受診率)は、年間1人当たり14回(全国平均12回)と高いにもかかわらず、お年寄り1人当たりの医療費は17万6000円(全国平均・34万3000円)で、全国平均の半分である。
沢内村の「生命行政」の素晴らしい成果を説明する役場の職員の話に、しばし無言でうなづくばかりであした。
役場の隣に「村立沢内病院」があった。病院長は村役場の「健康管理課長」を兼ねており、保健婦さんは病院の中の受付の隣に「健康相談室」があって、そこで全村民の健康カードをもとに相談・指導にあたっている。
また、50歳になれば半ば強制的に検査入院させて健康チェックをしているという。
これが本当の行政であり、基本理念の確立と実践に・・・ なるほど日本一、いや世界一だ ・・・と感銘を受けた。
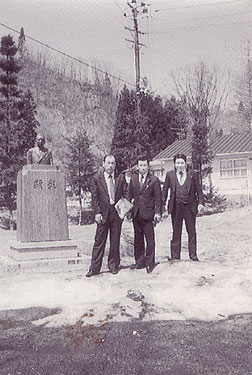
沢内村立病院前庭 故・深沢村長像前にて
続いて、国指定重要有形民俗文化財の“マタギの狩猟用具”などがある「碧祥寺博物館」を見た。岩手の山奥の生活用具など、民俗資料が所狭しと並んでいる。
岩手の厳しい生活を知らない者にとって、また、初めて見るということもあって、一つ一つの展示物から受けた印象は強烈であった。
< 沢内村を訪問したのは27年前の1982年。諸国行脚を20年前に発行した時の文章を、今回ホームページに載せるためにパソコンを打っていると、今日の赤旗新聞(09年8月10日)に、元・沢内村長、大田祖電さん87歳が盛岡市での共産党の演説会で“応援演説”をした記事が出ている。訪問した当時村長で、壁祥寺の住職だった。
【参考に引用する】
『 昭和35年(1960)日本で初めて、65歳以上の老人医療費の10割給付を実施した。翌36年さらに年齢を下げ、60歳以上無料にした。深沢さんは 「医療費無料化は先進諸国のすべてがめざしているところだ。国民の命を守るのは国の責任だ。しかし、国がやらなければ、やるまで(村が)やろう。国は必ず私の後を追ってくる。」・・・と進んでいきました。今度の総選挙で、深沢まさおの精神に一致するのは共産党だと思います。政治哲学もなければ、理論もないような考え方で日本の政治は任せられません。 』 ・・・・・ 訪問してから27年。日本の現状は、政治は・・・・・。 >
昨日と同じ道を引き返し、東北道を南下。築館ICでおりる。
宮城県迫町のU君がインターまで迎えに来てくれた。U君は、私の親せき筋の関係者で、いまこの町で 「信濃庵」というソバ屋をやっている。
共産党の町議の方も来て、一緒にそばを食べながら「減反問題など」懇談。
芭蕉は、石巻からこのあたりを通って中尊寺へ行ったそうだ。
さて、これから今夜の宿泊予定地の松島へ行くのであるが、U君が涌谷町の黄金山神社まで案内してくれるというので、彼の自動車の後をついてゆく。
≪黄金山神社≫
奈良時代に“金”が発見されて、奈良の大仏の金メッキはここから献上されたものが使われたそうである。
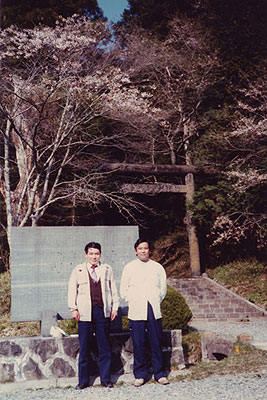
黄金山神社にて U君と
≪ 松島 ~七ヶ浜へ ≫
自動車できた便利さで、8年前に泊まった奥松島の“月浜”まで行ってみた。浜もニイヤもそのままであった。
ホトトギスの声を聞いた大高森の松も、同じように青かった。松島湾の月浜に対して突き出ている“七ヶ浜町”の「松ヶ浜」に今夜の宿をとることにした。
“ 音に聞く 松が浦島 けふぞ見る
むべも心ある 尼は住みけり ” (素性法師)
芭蕉も「松島」のところでふれている。
― 佳境絶景、松島におとらず ――
≪4月24日・壺の碑≫
塩釜の中卸市場でクジラの肉をお土産に買い、多賀城へと向かう。
奈良~平安時代にかけて中央政府の出先として、役所の置かれていたところである。多賀城址は暖かそうな小高い丘の上にあり、今は史跡公園として保存されている。 城址に立ち往時をしのぶ。
丘を下ると、昔の城の表門あたりに、芭蕉も見た“壺の碑”(つぼのいしぶみ)がある。
その横には芭蕉の句碑 “ あやめ草 足に結ばん わらじの緒 ” があった。
ここにきて、坂上田村麻呂を想い、芭蕉を想いながらしばしたたずむ。
この石碑の周辺も公園になっており、桜が満開で昔をしのぶにはとてもよいムードである。
この後、東北歴史資料館に行く。複製の「壺の碑」があった。

多賀城址
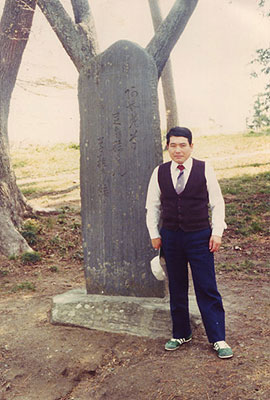
あやめ草碑前にて |

壺のいしぶみ・複製、前にて |
≪青葉城から杜の都をのぞむ≫
伊達政宗62万石の城下町である。青葉城より見た杜の都は、欅の芽吹きが素晴らしかった。
いよいよ帰路につく。安達太良サービスエリアで一休みし、栃木、群馬から軽井沢、佐久の野辺山の宇宙観測所を通り、小淵沢から駒ケ根に帰着。
時計の針は25日になっていた。
この旅行に先立ち、三沢ミュージックの三沢照男さんに「バッハ」の曲をテープにとってもらい、それを聞きながら旅をした。
☆ ブランデンブルグ協奏曲・全曲 ☆ バイオリン協奏曲・第1番、第2番
☆ 2つのバイオリンのための協奏曲。 ☆ バイオリン協奏曲・ト短調
☆ トッカータ・ハ短調 ☆ バルテ―タ・第2番 ☆ イギリス組曲
・・・ など、6時間分のテープで、「バッハ」漬けの旅でもあった。
<走行距離総計 1665Km>

|


![]()